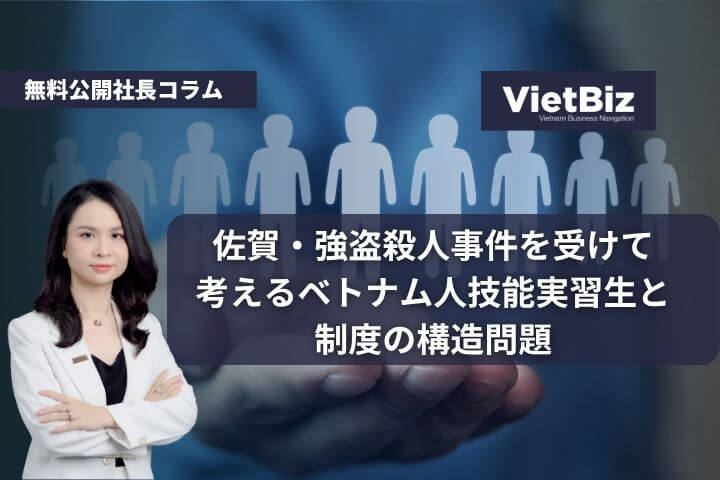技能実習制度は現代の奴隷制度として、日本の労働者と経済社会を蝕む構造である。
皆さま、こんにちは。ONE-VALUE株式会社の代表のホアです。
2025年7月、佐賀県伊万里市の住宅で、日本語講師の椋本舞子さん(40)がナイフで襲われて死亡し、70代の母親がけがを負うという事件が発生しました。現場近くに住むベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者(24)が、現金およそ1万1千円を奪おうとした強盗殺人などの疑いで逮捕されています。住宅の中には荒らされた跡があり、容疑者と被害者親子に面識はなかったとされています。
亡くなられた椋本舞子さんのご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、けがを負われたお母様の一日も早いご回復を願っております。
私はこの事件をきっかけに、ベトナム人(特に技能実習生や日本語学校生)による犯罪が近年増加している背景を分析し、日越両国の社会が問題解決に向けて考える一助となることを願い、本稿を執筆します。
技能実習制度は名ばかりの「技能移転」、実態は現代の奴隷制度ではないか。
技能実習制度は1993年に日本で導入され、「発展途上国への技能移転」を目的として多くの若者をアジア各国から受け入れてきました。しかし、30年が経過した今、制度は形骸化し、実質的には「低賃金労働力の供給システム」へと変質しています。
ベトナム、ミャンマー、フィリピンなどから来日した若者は、野菜の選別、皿洗い、ごみ処理、介護など、比較的単純な仕事や過酷な仕事に就かされています。
職場変更は原則認められず、賃金交渉権もなく、劣悪な環境の寮に押し込められ、差別やハラスメントがあっても相談先は限られています。
実習生は「送り出し機関」に多額の費用を支払い、日本の「受け入れ企業」に“安価な労働力”として提供される構造となっています。
2023年には日経新聞もこの制度を「現代の奴隷制度」と批判し、早期の廃止を提言しました。18〜19世紀にアフリカの人々が奴隷としてアメリカに売られた構図と酷似しており、現代では「貧困層の若者が借金をして自らを売る」仕組みへと姿を変えています。
なお、政府はすでに2027年4月をもって技能実習制度を廃止し、「育成就労制度」へと移行する方針を打ち出しています。制度の理念転換が明言されたこと自体は評価できます。
しかし現場では、「制度の名称だけが変わり、実質的な構造は変わらないのではないか」という懸念の声も少なくありません。制度の再構築が、真に労働者の人権を守り、対等な関係に基づく受け入れ制度となることを切に望みます。
技能実習制度は日本社会と経済にも悪影響を及ぼしている
1989年のバブル崩壊以降、日本は30年以上にわたってデフレと経済の停滞に直面してきました。
「価格を上げないこと」が美徳とされ、企業はその実現を人件費の抑制、特に労働コストの削減に求めました。
労働力不足に直面しても、企業は賃上げではなく、外国人労働者の低賃金投入によってコストを維持する方向に進みました。
その結果
・日本企業の約99.7%を企業数ベースで占める中小企業は価格交渉力が乏しく、安価な外国人労働力に依存せざるを得ません。
・大企業は資金力と立場を活かして、下請け企業に対する価格引き上げ要求を拒み続けています。
安価な商品が長年ほぼ同じ価格で売られ続ける一方で、労働者(日本人を含む)の賃金はほとんど上がっていないのが現実です。そのひずみの一端が、外国人犯罪の増加というかたちで社会に表れ始めています。
日本社会の構造的課題と責任の所在
一方、大企業は優秀な外国人材を雇用できる十分な資金力を持つものの、自社が取引している中小企業の価格引き上げには応じようとしません。購買や製造委託などの取引関係において、交渉力で圧倒的に優位に立っており、下請け企業が価格を上げようとするならば、経団連や政府による強い方針転換がない限り、それを実現することは困難です。このような構造の中で、誰がどのような役割を果たし、何が問題の本質なのか。以下では、制度の歪みを生み出している三つの主要な要因について考えてみたいと思います。
1.質の低い送り出し機関
1人あたり数十万円〜100万円以上の手数料を徴収しながら、生活指導や問題発生時の対応支援を十分に行っていません。労働者が日本で困難に直面しても、実質的には守られていない状況が続いています。
2.日本政府の誤った政策判断
時代に合わない制度を温存し、労働市場の改革を行わず、深刻な人手不足を「安価な外国人労働力」でその場しのぎ的に埋めようとしてきました。日本の国際的地位にふさわしい人材戦略を描かず、持続的な成長のための制度設計がなされていません。
3.技能実習生を受け入れる日本企業の構造的依存
「安さこそが正義」というビジネス倫理が根づいており、結果的に貧困層の若者を搾取することで事業を維持する構造になっています。
※ただし、前述の通り、日本の経済構造において企業がこのような選択をせざるを得ない背景があることも理解しています。
フィ・ホアからの提言 日本は今こそ変革すべき時
未来の持続可能な社会のために、日本は以下の改革を進めるべきです。
- 技能実習制度の廃止と実質的な制度改革
理念と実態が乖離した制度は廃止し、選抜された人材に対し、透明で公正な労働ビザ制度を設けるべきです。
※技能実習制度は将来的に廃止されることがすでに決定しており、2027年4月から「育成就労制度」への移行が予定されています。ただし、制度の名称変更にとどまり、実態が変わらないことのないよう、根本的な改革が求められます。 - 価格と賃金の是正
「安さは善」という価値観を見直し、適正価格を通じて人・技術・サービスに適切な対価を支払う経済文化を取り戻すこと。 - 高度人材ビザ制度の整備
世界中の優秀なエンジニアや研究者、起業家が日本を選ぶような待遇と教育・生活環境を提供し、「頭脳の流入」による国力強化を図るべきです。 - 国際教育・生活環境の整備
英語で学べる大学や国際学校を拡充し、背景の異なる人材が安心して子育てや生活を送れる都市をつくる必要があります。 - 「安価な労働力」から「価値創造」へ
2023年時点の日本における外国人比率は約2.4%。ドイツ約18%、イギリス約14%、フランス約13%、カナダ約23%、アメリカ約15%。
人材の多様化は避けられない流れであり、今求められているのは「安さ」ではなく「共に価値を創れる人材」との出会いです。
おわりに
外国人を受け入れることは、先進国の多くが将来への投資として取り組んでいる重要な政策です。
しかし、「安く使うため」の受け入れは、やがて社会の信頼を失い、自国の衰退を招くことになります。
私は日本という国が本当に好きです。だからこそ、この社会が人間の尊厳を大切にし、持続可能な未来へと進んでいくために、今こそ制度を見直し、変革に踏み出してほしいと強く願っています。
フィ ホア(ONE-VALUE株式会社 代表取締役)
2008年、日本政府 (MEXT)の国費留学生 として来日。大阪大学大学院、経済学研究科経営学系を修了後、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に入社。ベトナム事業拡大のリーダーに就任し、多くの日本企業のベトナム進出を成功に導く。約10年にわたる経営コンサルティング実務経験を有し、多くの日系大手企業に対して、ベトナムに関する経営コンサルティング業務を提供してきました。主な専門領域は再生可能エネルギー、木材製造、医療、IT、農業、教育等。
2018年、ベトナムに特化した経営コンサルティング会社、ONE-VALUE会社を設立。ONE-VALUEでは、日本とベトナムの経済・ビジネス関係の活性化、日本在住の外国人人材の生活向上という2つのビジョンを掲げています。